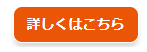相続手続きでは、どのような財産があるかを正確に把握することが重要です。財産の全体像がわからないまま遺産分割を進めると、不公平な分配や後のトラブルにつながる恐れがあります。また、財産にはプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるため、見落としは禁物です。
●相続財産の種類とは?
相続の対象になる財産は、大きく分けて次のようなものがあります:
・金融資産:預貯金、株式、投資信託、債券、現金など
・不動産:土地、建物、マンションの所有権、借地権など
・動産:自動車、貴金属、美術品、家具、骨董品など
・権利:貸付金、著作権、ゴルフ会員権などの各種権利
・マイナスの財産:借金、ローン、未払いの税金、連帯保証など
このように、目に見える財産だけでなく、見えにくい権利や負債も相続の対象になります。
●財産を調査する方法
財産の調査は、まず被相続人の通帳や郵便物、契約書、確定申告書などを確認するところから始めましょう。
・預貯金:通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵送物など
・不動産:登記簿謄本(法務局で取得可)、固定資産税通知書
・株式・投資信託:証券会社からの取引報告書、口座番号など
・借金やローン:借入契約書、カード明細、督促状の有無を確認
・保険:生命保険・医療保険の契約書や保険証券
なお、不動産の所在地が不明な場合は、市区町村の名寄帳を活用すると、名義人ごとの所有物件が一覧でわかることがあります。
●財産の評価と一覧表の作成
財産を洗い出したら、それぞれの評価額を確認しておくことが大切です。相続税の申告や遺産分割協議にも必要になります。
・不動産は「固定資産評価額」や「路線価」などを参考にする
・上場株式は、死亡日の終値で評価
・預貯金は死亡日時点の残高
これらをもとに「相続財産一覧表」を作成しておくと、相続人同士での話し合いがスムーズに進みます。
●注意すべきポイント
被相続人名義の口座は、死亡後に凍結されるため、相続人が勝手に引き出すとトラブルになる可能性があります。
保証債務や借金が後から判明することもあるため、慎重に調査を進めましょう。
相続放棄や限定承認を検討する場合は、財産の全容を把握してから判断することが必要です(原則として3か月以内)。
財産の把握は、相続を「公平かつ円満」に進めるための土台づくりです。曖昧なままにせず、時間をかけて丁寧に調べましょう。