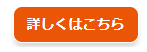相続手続きを進めるうえで、遺言書の有無は非常に重要です。遺言書があるかないかで、相続財産の分け方や必要な手続きが大きく異なります。
遺言書は故人の最終意思を反映したものであり、民法に定められた法定相続よりも優先されます。そのため、遺言書の有無を最初に確認することが、スムーズな相続のカギになります。
●遺言書の種類と特徴
遺言書には主に3つの形式があります:
・自筆証書遺言
故人が自分で全文を書いたもの。家庭で保管されていることが多く、見つけにくい場合もあります。発見された場合は家庭裁判所での「検認」が必要です。
・公正証書遺言
公証役場で公証人が作成し、原本が保管されているもの。最も確実で安全な形式で、検認が不要です。公証役場で調査すれば、本人が遺言を残していたかどうかを確認できます。
・秘密証書遺言
本人が書いた内容を封印し、公証人が証明する形式。あまり利用されておらず、実務ではほとんど見かけません。
●遺言書の探し方と注意点
遺言書がある場合、それに基づいて遺産を分けることになります。まずは、以下のような場所を探しましょう:
・故人の机や金庫
・預金通帳や重要書類と一緒に保管されているケース
・家族や信頼する知人が預かっている場合も
公正証書遺言かどうかを調べたい場合は、全国の公証役場で「遺言検索システム」を使って照会できます。
ただし、遺言書があっても内容に不備があったり、相続人が無視できない内容であったりする場合は、法的トラブルに発展することもあります。たとえば、遺言により特定の相続人の取り分が大きく減らされた場合、遺留分侵害額請求が認められる可能性があります。
●遺言がある場合の手続きの流れ
遺言書の有無によって、遺産分割の進め方が異なります。
・遺言がある場合
基本的には遺言に従って分割・名義変更を行います。ただし、自筆証書遺言の場合は「検認」後でないと正式な手続きに使えません。
・遺言がない場合
法定相続分に基づいて、相続人全員による「遺産分割協議」が必要です。協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判を経ることになります。
遺言書は相続の「地図」とも言える存在です。あるかないかを早期に確認し、内容を正しく理解することで、相続人同士のトラブルを避けることができます。